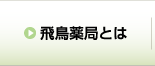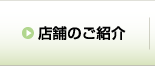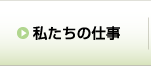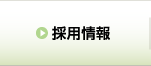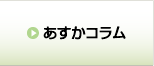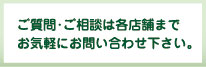お薬研究所 : 2010年11月号-#3 [2010.11.25up]
お薬研究所では「薬局でのこんな相談」や「病気の話」など、皆さまの健康に役立つ情報を掲載しております。
» こんな相談「アルコール」
├ 1. 概要
├ 2. 薬はどのように効くのでしょう
├ 3. アルコールの生理作用
├ 4. 肝臓にある酵素
└ 5. 意外と知らないアルコール含有食品
これまでの記事(直近3件)
» 2010.11.17 お薬研究所:2010年11月号-#2 サプリメント「茶カテキン」
» 2010.11.09 お薬研究所:2010年11月号-#1 病気の話「腰痛」
» 2010.10.28 お薬研究所:2010年10月号-#3 サプリメント「レスベラトロール」
こんな相談「アルコール」
 高血圧や脂質異常症、糖尿病などの生活習慣病治療のために毎日決まった薬を飲む方に多いのがこんな相談です。そもそもこうした生活習慣により発症しているわけですから、基本は極力控える事が大切です。
高血圧や脂質異常症、糖尿病などの生活習慣病治療のために毎日決まった薬を飲む方に多いのがこんな相談です。そもそもこうした生活習慣により発症しているわけですから、基本は極力控える事が大切です。
酒は百薬の長と言われます。“徒然草”の中で「百薬の長とはいへど、よろづの病は酒よりこそ起これ」とあり、まさしく生活習慣病の要因の一つである事がわかります。
医学的な適量とは、アルコールとして30ml/日で 日本酒1合、ビール大瓶1本、ウィスキーであればシングル3杯程度が適量と言われています。しかし、薬を服用するとなれば話は別です。アルコールの薬に対する影響をしっかりと理解し正しく飲んでこそ薬の効果が期待できるのです。
薬はどのように効くのでしょう
このような循環を繰り返してゆく間に、徐々に薬は体の外に出てゆくのです。

アルコールの生理作用

アルコールには、それ自体に中枢神経抑制作用や血管拡張作用があります。したがって、以下の薬と併用する事でその作用が増強されます。
肝臓にある酵素
肝臓には、薬を代謝する酵素がたくさんあります。その中でも“チトクロームP450”という酵素はその代表選手。薬の代謝のおよそ80~90%に関与していると言われています。この酵素で代謝される薬を併用すると、限られた数の酵素はフル稼働しますが代謝の順番待ちの薬が体の中で循環します。つまり薬の効果が増強される事になるのです。

アルコールは消化管で吸収され、その90%が肝臓で代謝されます。したがって、一緒に服用する事で薬の効果が強まり、体調に影響します。
さらに、アルコールを常用していると肝臓の酵素はその数を増やして、代謝がスムーズにゆくように働きます。その結果、通常の量では薬が効かないといった困った現象が起こる可能性もあります。それでは、体に入ったアルコールはどのくらいで代謝されるのでしょう?代謝には個人差がありますが、一般的に60~70Kgの人で1時間に代謝できるアルコール量は7g程度と言われています。そして、飲んでから1時間後くらいに血中濃度は最高点に達し徐々に減少します。たとえば、医学的適量であるとされるビール大瓶1本 or 日本酒1合 or ウィスキーシングル3杯 が代謝されるのにはおよそ2~4時間を要します。したがって薬の服用と飲酒は4時間以上あける事が望ましいのです。晩酌の習慣のある人が、夕食後や寝る前の薬を飲む時には注意が必要です。
意外と知らないアルコール含有食品
エタノールの含有率が1%以上の物を酒類としていますが、医薬品として販売されているドリンク剤などは課税対象外であるため、比較的含有量の多い製品もあり注意が必要です。たとえ含有量は少なくても1日に何本も飲んだり、定期薬をドリンク剤で飲んだりなどは避けるようにしなければなりません。
また、清涼飲料水や炭酸飲料、栄養調整食品にもアルコールが含まれている事もあり摂取する量にもよりますが、注意は必要です。
薬は、コップ1杯の水で指示どおり服用する事で薬の持つ効果が最大限に生かせるのです。思わぬ副作用をまねく事のないよう注意しましょう。